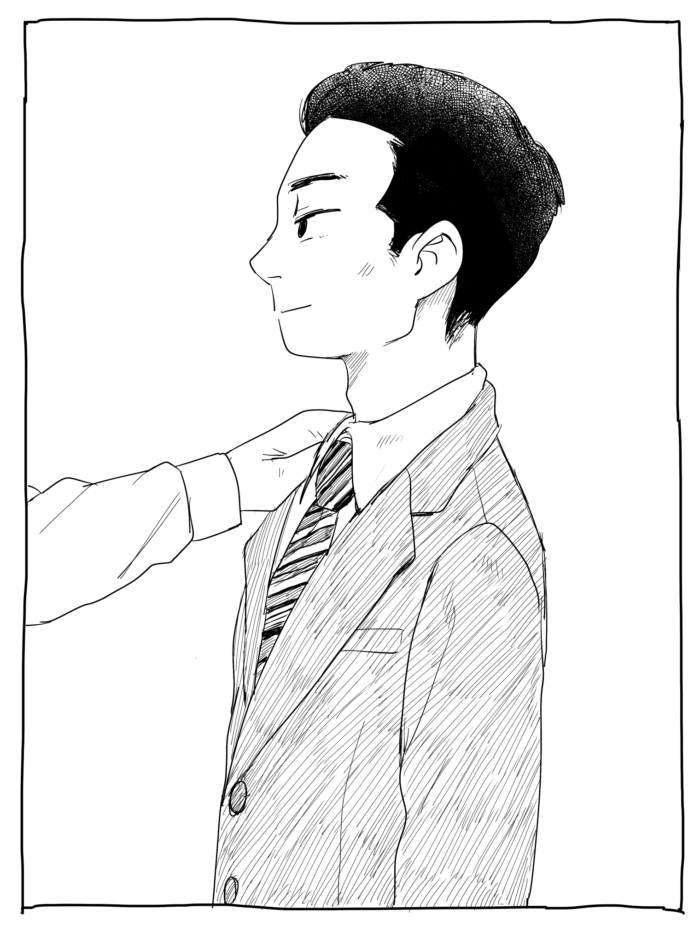
1952年(昭和27年)3月、戸田青年団の定期総会が開かれた。
場所は家の裏にある戸田小学校の教室。30人ほどが集まった。
真木家では克義と潔が参加した。
克義は何年か前から入っていたが、潔は前年5月の就職後に入団したため、今回が初めての総会だ。潔と5人の同級生が最年少の新入団員だった。
戦時中、青年団は国の手足となって戦争を末端で支えた。しかし戦後は、全国の若者が自分たちで立ち、戦争で荒れた故郷を支えようと、様々な活動に取り組んでいた。
それでも、やっている人間がすぐ変わるわけではない。
戸田青年団でも、中心になって仕切っていたのは40歳になろうかという年長者たちだった。
総会は夕方から始まった。同じ顔ぶれの役員を承認し、年間の計画を話し合う。議論というほどのものはなくシャンシャンで終わろうとした時、潔が手を挙げた。
「2月にここであった演芸会の事です。あれは何とかした方がいい」
潔は話し始めた。
毎年2月の旧正月に合わせ、戸田では青年団主催の演芸会が開かれていた。
戸田小学校の講堂を借りて行う。夕方に始まり、小学生から年寄りまで歌や踊りや劇などを披露する。地域の人たちがこぞって訪れるため毎年盛況だった。
問題は後始末だ。
人々はお菓子やゆでた栗の実を持ち寄り、食べながら眺める。酒も飲む。そしてそれらのゴミは、すべてその場に残して帰るのが、これまでの地域の習わしだった。
真っ暗な中で辺りにゴミを撒き散らしながら観るのだ、人が歩けば踏んづけていく。翌日の講堂はゴミが散らかっているだけでなく、床は栗のカスなどが擦り付けられて真っ黒に汚れていた。
それを先生と子どもたちが午前中かけてゴミを片付け、床を拭いてきれいにする。これは戸田小学校に限ったことではなく、地域で普通に行われていたことだった。
潔はこの2月、初めて演芸会に出て驚いた。翌日店を訪れた先生がこぼしていたこともハレから聞いていた。
「あれは余りにもひどい。みんなの建物をを青年団が借りて行う行事です。きちんときれいにして小学校に返すのが筋じゃないですか。やり方を変えた方がいい」
潔はそう締めくくった。当然のことを話しているのだから、みんな賛同してくれると思っていた。
「そんな必要はない」
会長がすぐに言った。
「学校は地域のものだ。地域の行事に使い、その後始末を学校がするのは当然だ。それに」
会長が潔を見て言った。
「ここでは、昔からずっとこのやり方でやってきた。まあ、お前は知らないだろうがな」
周りを見回す。意見を言うものはいなかった。
「ではこれで総会はお開きとしよう。さあ懇親会だ」
議事は1時間程度で終わり、恒例の宴会の準備が始まった。
潔はこの場にいるのがバカバカしくなった。
同級生たちも居心地悪そうな顔をしている。
「おい、うちでトランプしようぜ」
「そうだな」
6人は戸田小を出て店に戻った。お菓子を買ってつまみながら店の奥の居間でコタツに入ってトランプをしていた。
午後9時ごろ、店に男たちがドヤドヤと入ってきた。
克義と何人か、6人より少し年上の人たちだった。
「お前たち、なぜ早くいなくなったんだ」
克義が言う。最初から詰問調だ。
「なぜって、総会が終わったんだからいいじゃないか」
潔が返す。双方の仲間たちは黙って潔と克義を見つめている。
「いやお前たち、後始末があるじゃないか」
「後始末って、何のだよ」
「酒飲みのだよ」
潔はコタツから立ち上がった。
「オレたちは酒を飲んでないし飲みたくないんだ。酒が飲みたいなら飲んだ人が後始末すればいいじゃないか。酒も飲まないオレたちが宴会が終わるまで待たなきゃならないなんて、そんな憲法がどこにある」
克義も声を張り上げた。
「憲法の問題じゃない。1年生が最後までいるのは当たり前だ」
「どこにそんな話がある。団員1人1人はみな同じ立場だ。飲みたい人が飲んだら、最後に自分たちで後始末すればいいだけじゃないか」
潔は言いながら、中学2年の時に先生の家の前で言われたことを思い出した。
「どうしてそんな、昔からある封建制をこの青年団に持ち込むんだ」
そう言って、克義をにらんだ。
すると潔の同級生たちも続いた。中学で初めて新憲法を学んだ世代だ。
「そうだ。日本は民主国家になったのにおかしいよ」
「主権在民の世の中だ。上に従うだけじゃダメだって先生が言ってた」
戦後の社会の成り立ちや原理原則を学んでいない克義たちには反論できない。
潔はさらに言う。
「さっきの演芸会の話でもそうだ。カツあんちゃは本当にあれでいいと思っているのか」
克義は一瞬息を飲んだが、仲間や潔たちを見回しながら言った。
「いや、あれはお前の言っているのが正しいと、俺も思うよ」
結局「上級生」たちは、そのまま学校に戻って行った。
数日後、近所に住む青年団の先輩から、潔たちは意外な知らせを聞いた。
「おい、会長たち、みんな青年団を辞めるってよ」
潔と克義のやり取りは、翌日には会長たちにも伝わった。
「どうやら今の若いものたちは、俺たちとは一緒にやれないようだな」
「新憲法なんて話までされちゃ、たまらんなあ」
「しかし、言っていることは正しいところもあるよな」
「もう俺たちが出しゃばる時代じゃないってことだな」
そんなやりとりがあって、結局30歳を超えるような長老たちが軒並み青年団を辞めることになったという。
「これからどうするんですか」
そう言う潔に、先輩は言った。
「どうもこうも、残った者でやるしかないだろ」
数日後、再度総会が戸田小学校で開かれた。
その先輩が会長、克義やその同級生が副会長に選ばれた。
「おい真木、お前、事務局長をやれ」
潔は会長から指名された。
「はいっ」
潔は二つ返事で引き受けた。騒動の引き金を引いたのだ、断れるわけがない。それに潔はこの時、はっきりと分かった。
地域の封建的な仕組みを一つづつ変えていく、ということはこういうことなんだ。
中学2年の春、先生に言われたことの意味が、潔の心の中で像を結んだ瞬間だった。
新執行部になっての戸田青年団は変わった。
小学校を借りた時には、最後にきちんと掃除をして返すようにして先生たちから喜ばれた。他にも地域の問題に取り組むようになった。隣の福岡町の興行主と仲良くなって、毎週映画の上映もした。戸田青年団の取り組みは、またたくうちに他の地域にも波及していった。
青年団の副会長と事務局長がいる。親はいない。
儲かりはしないが、店は若者たちの格好の溜まり場になった。
そこに春、ラジオがやってきた。郵便局に売りに来た中古のものを潔が月賦で購入したのだ。
ニュースを聞き、世の中の動きを知るようになった。
聞こえるのはNHKのみ。民放の岩手放送(現IBC岩手放送)がラジオ放送を始めるのは1年半ほど後のことだ。
4月、サンフランシスコ講和条約発効、日本の主権回復、日米安全保障条約発効。
5月、血のメーデー事件。
そして4月に始まったラジオドラマ「君の名は」。
放送のある木曜夜8時には、近所の若者がこぞって店に集まり耳を澄ませた。